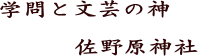|
|
二条為冬卿と南北朝時代
|
鎌倉幕府にかわって後醍醐天皇の治世がはじまった建武の新政の二年目、
藤原定家の子孫であり歌道を継ぐ家に生まれた二条為冬卿にも時代の波が押し寄せます。
文人である為冬卿が一軍の将に任じられ、足利尊氏討伐の大いくさに加わることとなったのです。
このとき、かつて討幕に功のあった足利尊氏は、鎌倉を占拠した北条残党を討つため
天皇の許しを得ないままに東海道をくだり、やがて鎌倉をとり戻したあともなかなか帰京しようとせず、
天皇のまつりごとに従わない姿勢をみせはじめていました。
ついに後醍醐天皇は尊氏追討を命じます。
その勅命は尊氏と対立していた新田義貞にくだりました。
義貞は天皇の皇子である尊良親王(たかながしんのう/たかよししんのう)を
奉じて軍勢を率いました。
そして二条為冬卿も公家大将として出陣することとなりました。
戦いのはじめは尊氏が朝敵とされることをさけて蟄居したこともあり、
新田軍が優勢で、尊氏の弟の足利直義(ただよし)をつづけてやぶります。
義貞は投降した敵を軍勢に加えながら進み、箱根をまえにして三島の伊豆国府から
先の行軍を二手にわけました。
箱根峠に新田義貞、足柄峠には尊良親王と義貞の弟の脇屋義助が向かい、
為冬卿も足柄峠近くの竹之下に親王とともに布陣します。
そしていよいよ新田勢が箱根をこえようとする戦況に、ようやく尊氏も参戦して、
為冬卿らの目前の足柄峠に現れます。
こうして歴史に残る「箱根・竹之下の戦い」が始まりました。
古典「太平記」によると、建武2年12月12日(1336年1月25日)、
合戦の火ぶたが切られます。
箱根口では義貞の軍が有利に戦いましたが、
竹之下では尊良親王・脇屋軍が尊氏にもろく破れて敗走します。
味方の寝返りにも合う中、二条為冬卿は尊良親王を守りながら命を落としたのでした。
佐野原に退いたという敗走軍のようすが「太平記」に記されています。
『中書王の股肱の臣下に憑み思し召されたりける二条中将為冬討たれ
給ひければ、右衛門佐の兵ども、返し合はせ返し合はせ、三百騎所々にて討死す。
これをも顧みず、引き立つたる官軍ども、われ前にと落ち行きける程に、
佐野原にも滞まり得ず、伊豆の府にも支へずして、搦手の寄手三万余騎は
、街道を西へ落て行く。』(岩波文庫:太平記)
(尊良親王がもっとも信頼していた二条中将為冬が討たれてしまい、
脇屋義助の軍勢も引き返しながら戦ったが、三百騎があちこちで討ち死にした。
これを顧みずに引く官軍は、われさきに落ちのびて佐野原に到着したが、
留まることができず、伊豆の国府も守れずに足柄峠側の
三万余騎は東海道を西へと敗走した。)
為冬卿の死を惜しんだのは味方だけではありませんでした。
この合戦は足利方の立場から書かれた軍記である「梅松論」にも記されており、
戦い二日目に尊氏は三島の国府を見おろす佐野山に陣を張ったとあります。
そして為冬卿とは盟友のあいだがらであったことから、
首を検分して愁傷の色が深かったと書かれています。
足利尊氏と同世代の歌人であった二条為冬卿とのあいだに、
深い親交があったことから、尊氏は大いに悲しんだという逸話が残されているのです。
さて箱根口では優勢であった義貞も退却を決意し、
新田軍は総崩れとなりました。
戦いは九州の大友氏、出雲の塩谷氏、そして婆娑羅大名で有名な
近江の佐々木氏(道誉)の寝返りが、そのゆくえを決めたと言われます。
そして形勢をくつがえした足利軍は今度は京まで攻めあがり都をおさえます。
二条為冬卿が佐野原にその生涯を閉じた、
「箱根・竹之下の戦い」は建武政権崩壊のきっかけとなりました。
しかし当時の武士は有利な方に寝返るのがつねであり、
のちに尊氏も一旦、京を捨て九州に敗走するなど、
都を支配する勢力はめまぐるしく交代します。
こうして戦乱の世は、国を分けて権力が対立し、
利害によりくみしては闘いにあけくれる南北朝時代へと移っていったのでした。
|
|
|
|